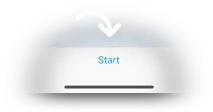『マスター・アンド・コマンダー/ザ・ファー・サイド・オブ・ザ・ワールド』は脚本家による意図的な欺瞞である。キリル・ナザレンコ

本記事は、海賊生活シミュレーションゲーム Corsairs Legacyの開発中に、Mauris studioが海洋テーマ全般と海賊ゲームというジャンルの普及を目的として制作した読み物です。プロジェクトの最新情報は、公式サイトのほか、YouTubeチャンネルやTelegramでご覧いただけます。
本記事では、キリル・ナザレンコが映画「Master and Commander: The Far Side of the World(マスター・アンド・コマンダー)」を考察します。
こんにちは。今回は、とても完成度の高い映画『Master and Commander: The Far Side of the World(マスター・アンド・コマンダー)』の分析に話題を絞りたいと思います。
私の話のジャンル上、当然ながら批評も含まれますので、気になったマイナス面にも触れますが、総じて『Master and Commander』は非常によくできた映画だと強調しておきます。
帆船時代の軍艦を主題にし、そのリアリティをここまで見事に再現した映画は、私の知る限り他にありません。それがこの『Master and Commander』です。
本作に登場する軍艦は本物のように感じられ、細部の小道具に至るまで、18世紀末〜19世紀初頭の本物のディテールが数多く取り入れられています。

映画『Master and Commander』:船内にある柱状の支柱
作中では、ときどき天井を支える丸い柱が室内に立っているのが映ります。この柱は小さな柱頭を持つ円柱のような形をしており、18〜19世紀初頭の軍艦で実際に使われていた支柱の姿をよく再現しています。これらの柱は船体構造上の役割だけでなく、見た目の美しさにも配慮した造形でした。もっとも、『Master and Commander』では、この柱はどちらかというと金属製に見え、これはむしろ19世紀中頃以降に典型的な仕様です。それでも、帆船映画としてここまで細かい小道具の選び方に気を配っているのは高く評価できます。
技術的な側面から見ると、『Master and Commander』の物語は2隻のフリゲート艦同士の戦いを軸に展開します。このようなフリゲート同士の一騎打ちは、ナポレオン戦争期というよりも、1812〜1815年の第2次米英戦争(アメリカ独立第二次戦争)に典型的な状況でした。この戦争では、アメリカとイギリスが再び戦火を交え、その中でアメリカ海軍のフリゲート艦が大きな役割を果たします。これは当時としても特異な現象でした。
アメリカのフリゲート艦は、イギリス、フランス、ロシアなどの同クラスの艦と比べると、まさに「豪邸」のような存在でした。1794年、アメリカが再び海軍を創設し、現在まで途切れることなく続く海軍の基礎を作り上げたとき、アメリカは戦列艦(戦艦)を大量に建造することを選びませんでした。イギリスほどの数の戦列艦を揃えることは不可能で、数で劣る以上、決戦では常に不利になると理解していたからです。その代わり、将来の戦争では、通商破壊戦、すなわち敵商船の拿捕を主戦略とすることを選びました。そのためには、非常に強力なフリゲート艦級の船を建造する必要があったのです。
こうしてアメリカ型フリゲート艦が誕生しました。当初は44門砲、やがて50門砲、さらに60門砲フリゲートへと発展していきます。船体は非常に長く、長いバッテリーデッキ(砲列甲板)に多数の大砲を載せることができました。

Master and Commander:18世紀末のアメリカ・フリゲート艦
同時に、アメリカは多くのフリゲート艦を建造したわけではなかったため、1隻1隻の造船品質は非常に高水準でした。なお、アメリカのフリゲート艦「コンスティテューション(Constitution)」は現在も実際に浮かんでいます。木造艦が200年以上にわたって水上にとどまり続けているというのは、たとえ修復を重ねているとはいえ、世界的にも極めて稀な事例です。
船体の材質には特別に処理したオーク材が使われました。アメリカは森林資源が豊富で、軍艦全体の数もそこまで多くなかったため、用いる木材を非常に厳選できたのです。その結果、これらのアメリカ・フリゲート艦は非常に頑丈で、第2次米英戦争の際、イギリスのフリゲート艦と一騎打ちになると、ほとんどの場面でアメリカ側が勝利を収めました。
これは、これまで一騎打ちの海戦ではフランス艦を打ち破るのが当たり前だったイギリス人の鼻を見事にへし折る結果となりました。しかし、それも無理はありません。イギリスの置かれた状況がまったく違っていたからです。イギリスは、ナポレオン戦争期の膨大な商船航路をフランス私掠船から守るために、膨大な数のフリゲート艦を必要としていました。そのため、必然的に20〜30門程度の比較的小型で軽量なフリゲート、あるいはフリゲートではなくスループやコルベットといった艦も多く造られます。スループやコルベットは、3本マストを持つものの、閉鎖された砲列甲板を持たず、1層の開放甲板に砲を並べる構造で、20〜24門程度の砲を搭載していました。
しかし、本作で描かれているのは、まさにイギリス側のフリゲート艦であり、『Master and Commander』の中で重要な役割を果たします。

映画『Master and Commander』:イギリスのフリゲート艦
劇中のイギリス艦は、ざっと見て30門ほどの砲を搭載し、そのほとんどが18ポンド砲であるように描かれています。しかし、18ポンド砲を装備した30門級のフリゲートでは、閉鎖甲板に24ポンド砲を並べ、上部には24ポンド砲カロネードを備えたアメリカの44門フリゲート艦と戦えば、実戦では勝ち目がほとんどありません。このタイプのフリゲートは後に各国で標準的な艦型となり、19世紀1840年代には多くの国が同様の艦を建造しました。そのころ、アメリカはすでに60門級フリゲート艦を建造し始めていました。
したがって、現実の海戦で30門級のイギリス・フリゲート艦がアメリカの重フリゲート艦と一騎打ちになれば、イギリス側にはほぼ勝ち目がありません。イギリス水兵の練度が高く豊富な戦闘経験を持っていたとしても、それは変わらないでしょう。ですが、映画はあくまで物語です。主人公が敗北してはドラマになりません。そこで、『Master and Commander』では敵をフランス艦に変更し、英語圏の観客が同じ陣営(イギリス側)に感情移入できるように設定されています。そして、映画の定石どおり主人公が最終的な勝者となるのです。
一方で、主人公が対峙するフランス・フリゲート艦の技術的スペックについては、劇中でもやや曖昧なままです。フランス艦は44門砲で、側板は沼地オークでできており厚さ2フィートだと説明されます。
さらに、『Master and Commander』では、イギリス艦の船長のもとに、水兵たちが自作したフランス艦の模型が持ち込まれます。ある水兵が、ボストンの造船所で建造中のその艦を見たことがあり、それをもとに仲間が模型を作ったという設定です。

映画『Master and Commander』:船長に見せられるフランス艦の模型
ここで少し滑稽な点が出てきます。撮影チームは、そこまで細かい点を詰め切れていなかったのでしょう。というのも、もし水兵たちが角材から船体の輪郭を彫り出した程度の木製模型であれば、私はまだ納得できたと思うからです。つまり、木のブロックを取ってきてナイフで削り、船の外形を再現しただけのものなら、船長にとっても多少の情報にはなったでしょう。
ところが、劇中で我々が目にするのは、17〜19世紀初頭に軍艦建造の際によく作られた「アドミラルティ・モデル」そのものなのです。造船技師は図面を読むことができても、大工たちは図面だけでは理解が難しかったため、どこにどの部材を取り付けるかを説明するためにアドミラルティ・モデルが作られました。この模型は、船体の骨組みを正確に再現しており、多くの場合、外板は貼られず、あるいは片舷だけに外板を貼り、内部構造が見えるようにしていました。アドミラルティ・モデルの最も重要な点は、甲板を支えるフレームとビームの格子状構造であり、これを理解・検討するために模型が作られていたのです。
ところが、ボストンで建造中のフリゲート艦をたまたま一度見かけただけの水兵が、その骨組みの構造を詳細に記憶し、それを他の水兵に説明し、その仲間がさらにアドミラルティ・モデル並みの精密模型を作る……というのは、ほとんど不可能な話です。これは完全なフィクションと言わざるを得ません。加えて、ビームの位置関係といった細部の構造は、敵艦と戦おうとしている船長にとっては実戦上さほど重要な情報ではありません。
さらに、船長が『Master and Commander』の中でその艦を「最新技術の結晶だ」と説明するとき、口にする技術用語自体は正しいのですが、その言葉と模型の構造があまり噛み合っていません。
もし新しさを強調したいのであれば、私は「丸い艦尾(ラウンド・スターン)」を採用している形にしたでしょう。艦尾上部には艦長の居室があり、その外側は窓と窓枠が並び、その後ろから砲門が続きます。この部分は基本的に台形に近い形をしており、角もはっきりしています。
その下には艦尾の切り欠きが始まり、そこからトランサム(艦尾平板)へとつながり、船体を閉じる平面の隔壁となります。トランサムはさらに舵柱(スターンポスト)へと接続されます。これは船体構造上の弱点で、特に航走時に問題になりました。トランサムが舷側に角度を持って接続されているため、強度が十分ではなかったのです。

映画『Master and Commander』:船の艦尾
そのため、18世紀末〜19世紀初頭にかけて、この艦尾部分を丸くする「丸艦尾」のアイデアが生まれます。上部の艦長室があるあたりは依然として四角形ですが、舵輪の上部あたりから艦尾を丸くし始める構造です。これにより、水の抵抗を減らすと同時に船体強度も向上しました。19世紀初頭には丸艦尾は一種の流行となり、本作でもそのような艦を描くことは十分可能だったはずです。
一方で、『Master and Commander: The Far Side of the World』における船首の鋭い線は、やややりすぎだと言えます。これは19世紀後半に登場した「クリッパー型の船首」、つまり非常に鋭く突き出した船首形状に影響を受けているのでしょう。
現在も海を航行しているモダンな帆船の多くは、非常にシャープな船首ラインを持ち、細長く突き出したノーズを備えていますが、それはすでに19世紀後半の船体設計です。19世紀前半には、「船首は丸みを帯びていなければならない」という考えに異論を挟む者はいませんでした。船首が波に突き刺さってはいけない――これは当時の設計において極めて重要なポイントだったのです。
船首線が鋭すぎると、船は向かい波または追い波の中で波に突き刺さる傾向があります。これが起きると、甲板上に留まることはほぼ不可能になり、非常に危険です。現代の蒸気タービンやディーゼル機関を備えた大型船であれば、船体も大きく、荒天時は内部に留まることもできるのでまだ耐えられますが、帆船時代はそうはいきませんでした。
帆船にとって、甲板上である程度快適に作業できることは存在の前提条件でした。甲板上には常に大勢の乗組員が働いているため、波が自由に甲板を洗うような状況は許されなかったのです。そのため、やや鈍い丸みを帯びた船首こそが、波に「よじ登る」ために必要な形でした。鋭い輪郭はむしろマイナス要素だったのです。
繰り返しになりますが、アドミラルティ・モデルのような精密模型を、口頭での説明だけから作り上げることはまず不可能です。撮影側が少しフィクションを盛りすぎてしまったのでしょう。脚本では水兵が模型を「削り出した」と書かれているのなら、それはただの木製ブロックであるべきで、これほど精巧な模型である必要はありません。
また、そのような精密模型を作る労力に対して、報酬がラム酒1杯だけというのも不釣り合いです。1人の水兵がこの模型にかかりきりになれば、2週間ほどは費やすことになるでしょう。それ以外に当直もあり、帆の作業もあり、睡眠時間も必要です。私なら、この水兵にはラム酒どころか数ギニー硬貨は渡すところです。
ちなみに、ギニー(guinea)は当時のイングランドの金貨で、額面は21シリングでした。これは1ポンド・スターリング(20シリング)よりも1シリング高い価値を持つ硬貨です。

映画『Master and Commander』:イギリスの金貨ギニー
当時、イギリス海軍の熟練水兵の年収は約10ポンドでしたから、この模型制作の仕事には2ポンド程度の価値はあったはずです。しかも、作中で艦長付きの給仕は、ラムではなくワインも出すと言うのですが、それでもまだ少しケチな印象です。
さて、ここからは嵐のシーン――映画『Master and Commander』における嵐の場面――について見ていきましょう。このシーン自体は非常によくできています。唯一気になったのは、衣服の着こなし方です。
もちろん、水兵たちがシャツのボタンを外し、髪も乱れているというのは当時のイメージとして正しいでしょう。しかし、雨と強風を伴う嵐の中では、どんな人間でも本能的に体を覆い隠そうとします。実際には、ボタンをかけて身を守りたいと思うはずです。ところが映画では、晴天でも荒天でも、水兵も士官もほとんど同じようにはだけた格好で登場します。
そして、現代映画お決まりの「主人公は帽子をかぶらない」演出も、帆船時代の現実からするとかなり不自然です。水兵たちはほとんど常に、少なくとも悪天候のときには帽子をかぶっていました。

映画『Master and Commander』:主人公の艦長
また、嵐の中で索具を切り落とすシーンは、ドラマ性を強調するためにやや引き延ばされていますが、そこまで不自然というほどではありません。ただし、実際に船から何が落ちたのかが少し分かりにくい。おそらく、マスト上部のトップマストが、ヤード(横帆の桁)と帆ごと折れて海に落ちたのでしょう。当然ながら、それらはロープ類につながったままで、これを切り捨てる必要がありました。さもないと、「漂流錨(フローティング・アンカー)」のような状態になってしまうからです。
この「漂流錨」という手法は、通常の操船でも使われました。嵐の中で船の速度を落としたいとき、予備のトップマストやヤードを三角形状に組み、その上から予備の帆を縛って海に投げ込むことがありました。この構造物が船の後ろに引きずられ、大きな抵抗を生み出し、船の速度を落とすことができたのです。
条件によっては、この方法が必要でした。しかし、『Master and Commander』で偶然生じたような意図しない「漂流錨」は非常に危険です。とはいえ、それによって直ちに船が転覆するというよりも、船の運動を大きく妨げることが問題でした。
嵐の中での行動には、2つの基本的な選択肢があります。1つは、「横漂い(リーヘッド)」の状態で風上に対して船を横向きにし、一部の帆を通常どおり張り、一部の帆には逆方向から風を受けさせる方法です。こうすると、船は風下に流されにくくなり、おおよそ同じ海域に留まることができます。場合によっては、ここにさらに漂流錨を追加して、流されるスピードを抑えることもありました。ただしその分、波や風、索具への負荷は増し、本当に強烈な嵐では横漂いは不可能でした。そのような時は、わずかな帆、あるいは専用のストームセイル(嵐用の小さな帆)だけを張って、どこかしらの方向へ進むしかありません。
もう1つの選択肢は、風下へ走る方法です。これは風向きに対して最も安全ですが、速度が非常に高くなり、意図しない方向へ大きく流される可能性があります。とはいえ、いずれの選択肢を取るにせよ、マストの一部がヤードや帆とともに海中でぶら下がっている状態は最悪ですから、切断してしまうしかありません。
嵐の中で水兵が海に投げ出されたり、折れたマストなどと一緒に落ちたりした場合、その運命はほとんど決まっていました。助かる見込みはほぼゼロです。帆走軍艦の水兵なら誰でも、船全体を守るためにはその犠牲を受け入れざるを得ないと理解していたはずです。

映画『Master and Commander』:亡くなった水兵を悼む場面
ところが映画では、海に落ちた水兵が延々と泳ぎ続けているように描かれ、周囲からも「こっちへ泳げ」と声が飛びます。しかし、10〜20メートルの高さから水面に叩きつけられれば、多くの場合即座に意識を失い、そのまま沈んでしまうのが現実です。もちろん映画として、観客に涙を誘うためには、彼の死をめぐって議論や感情的なやり取りを描く必要があったのでしょう。
18世紀の人々が仲間の死に対して冷淡だったと言いたいわけではありません。しかし、そのような状況では誰もが結果を理解しており、仲間の死を悼み、語り合うのは、嵐が過ぎ去ってからでした。嵐の最中は、誰もがそれどころではなく、自分の作業に追われていたのです。亡くなった水兵の持ち物を分配する場面なども、嵐の後に描けばよかったでしょう。そのほうが、水兵たちが実際には仲間を悼んでいたことを強調できたと思います。
また、海での「財産相続」の場面も描けたはずです。身内のいない水兵の場合、その最も親しい友人が遺品を受け継ぐ、という慣習がありました。あるいは、亡くなった水兵の妻や母に渡すために、遺品を預かる人物を描くことも自然だったでしょう。そのような場面を通じて、水兵たちがどのように仲間の記憶を引き継いだのかを表現できたはずです。

映画『Master and Commander』:乗組員が仲間の死を悼むシーン
最後に、白兵戦(乗り込み戦)のシーンについて触れましょう。『Master and Commander』では、まず敵艦のマストを狙い撃つという船長の戦術が描かれています。
海戦でマストを狙うのは戦術として理解できますが、劇中のような拳銃距離に近い接近戦では、むしろ船体や甲板を狙うべきです。一方で、「マストを狙う」という発想自体は十分妥当であり、おそらく脚本家たちは、フランス海軍が砲撃で索具を狙う傾向があったという史実を踏まえて、この要素を盛り込んだのでしょう。フランス側は18世紀を通じて、「少なくともイギリスとの海戦を引き分けに持ち込む」ための理論研究と戦術開発を続けていました。
しかし、そのために大砲の砲架から車輪を外す必要はまったくありません。ごく日常的な方法で、どの艦載砲も10〜15度程度までは砲口を上に向けることができます。これはかなり大きな仰角です。距離100メートルで砲を15度持ち上げれば、砲弾はほぼ10メートルの高さまで飛びます。それだけでもマストを狙うには十分でした。
さらに、どうしても仰角を増やしたければ、砲架の前輪の下に木片の楔をかませばよかったのです。実際、嵐のときに砲を固定するときには、後輪の下に楔を打ち込んでいました。砲は砲門の内側から砲門蓋に押し付けるように固定し、その状態で楔を噛ませていたのです。もちろん、砲が反動で後退しても、両舷から延びる「トラウザー(ケーブル)」や、砲を舷側に引き寄せるための滑車つきのロープがその動きをしっかりと制限しました。

映画『Master and Commander』:艦載砲
発射後、砲はロープに引かれて後方へ勢いよく後退します。滑車を通るロープ(ホイスト)がその反動を抑え、最後はトラウザー(砲をつなぐ太いロープ)の張りで止まります。トラウザーは両舷に固定され、その中央部が砲の後部、もしくは砲架の特別な穴を通っていました。こうして砲は安全な位置まで後退し、再装填が可能になります。
車輪を外すのがまずかったのは、再装填が難しくなるからではありません。問題は、砲が発射の反動で暴れたとき、甲板を激しく傷つけることでした。木製の車輪でさえ甲板を痛めるのに、それがなくなれば損傷はさらにひどくなります。しかも水兵たちは裸足で働いていたため、通常射撃のあとでさえ足裏に刺さる木片(トゲ)の量が相当なものでした。
後輪を外してしまえば、甲板は文字通りズタズタになるでしょう。甲板は完全に平らではなく、板も舷の方向とは直交しているため、砲は板目に対して横方向に動きます。板が一本でも少し浮いていれば、砲が横転する危険性もありました。ですから、実際に砲架から車輪を外すようなことは、まず行われなかったと断言できます。
ちなみに、映画『Master and Commander』では、イギリス軍艦の砲に火打ち石式の点火装置が取り付けられている様子がよく描かれています。これは小銃と同様の仕組みで、火縄銃のように火のついた導火ロープを持ってくるのではなく、水兵が紐を引くと火打ち石が鋼鉄に当たり、火花で火薬皿の火薬に着火し、その火が火道を通って砲身内の装薬に達して発射される方式です。
この方式は本質的にイギリスの発明であり、19世紀初頭までには、イギリス艦隊の全ての艦載砲に火打ち石式の点火装置が装備されていました。確かにこの仕組みには欠点もあり、100%の発火を保証するものではなく、湿気にも弱いという問題がありました。それでも、発射速度と安全性の面で、これは大きな前進でした。

映画『Master and Commander』:乗り込み戦の場面
その後、映画『Master and Commander』は乗り込み戦(ボーディング)へと移ります。ここで船長は、まるで西部劇のカウボーイのように両手にピストルを構えて甲板を駆け回り、次々と向きを変えながら撃ちまくります。
しかし、雷管式(キャップロック)の登場以前、火打ち石式の銃器は決して100%の信頼性を持つものではありませんでした。雷管式が狩猟用に現れたのは19世紀1820年代、軍用で広く普及するのは、爆薬水銀を小さな銅製のカップに詰めた雷管を採用した1840年代以降です。雷管が導入されることで、ようやくほぼ100%に近い着火率が実現されました。
統計によれば、例えばイギリス製の火打ち石式銃の錠前は非常に高品質で高価でしたが、それでも50〜60発に1回は不発でした。フランス製では15〜20発に1回は不発だったと言われます。つまり、15〜20回撃てば少なくとも1回は弾が出ないのが普通だったのです。
そこへ持ってきて、ピストルを腰帯にぶら下げたり、荒れた甲板を走り回ったりすれば、火薬皿の火薬がこぼれたり湿ったり、弾丸そのものが発射前に抜け落ちる可能性すらあります。ですから、両手にピストルを持って歩き回るという行為自体は不可能ではありませんが、かなり危険でもあります。
18〜19世紀初頭の人々は、通常、右手に剣やサーベル、カットラスといった白兵武器を持ち、左手にピストルを持っていました。ピストルが不発でも、白兵武器なら必ず動きますからね。
実際、多くのヨーロッパ諸国の陸軍では、ナポレオン戦争期であっても、特に徒歩で戦う下級・中級士官はピストルを携行しないのが一般的でした。彼らは、「撃つのも刺すのも兵士の役目であり、士官は指揮を執るのが仕事だ。護身にはサーベルで十分」と考えていたのです。
唯一、オーストリア軍では徒歩の士官にもピストル携行が義務づけられていました。騎兵の場合はまた別で、鞍には2丁のピストルが常備されていましたが、これは馬が運ぶ荷物です。海戦の場合、乗り込み部隊の武装は、基本的に白兵武器と補助的なピストルという組み合わせでした。
次に描かれるのは、敵艦への乗り込みシーンです。映画では、主人公たちがロープを伝って、まるでターザンのように敵艦の甲板へ飛び移る場面があります。とはいえ、これは1〜2回、短い距離でだけ行われています。また、フランス側の兵士たちが死体の下に身を潜め、イギリス兵が甲板に乗り込んだところで一斉に飛び出すという「トリック」も描かれています。ドラマチックな演出としては面白いのですが、現実の戦闘では、まず不可能な状況です。

映画『Master and Commander』:マスト上の射手
また、私が少し驚いたのは、映画『Master and Commander』では海兵隊(マリーン)がマストの上で狙撃を担当していることです。現実には、海兵隊員がマストに登ることは非常に稀でした。
そもそも、船員全員がマストに登れたわけではありません。帆走軍艦の乗組員のうち、マスト上の作業を担当したのは全体の10%程度にすぎませんでした。純粋に水兵だけを取り出しても、上部で働ける者は20〜25%程度でした。そこから、射撃がうまい者を選抜し、フィリバスター銃と呼ばれる長銃身のライフル銃を持たせていました。銃身長は1.5メートルにも達し、高い精度で狙撃できました。
マストの上から射撃するのは、こうした専門の射手たちの役割でした。海兵隊の兵士がマストの上まで登り、揺れるトップマストの上から射撃するのは、現実的ではありません。そのためには、単に隊列射撃に熟練しているだけでは不十分で、マスト上での作業経験が必須だからです。
海兵隊員に求められたのは、まず素早い射撃であり、命中精度はその次でした。ここでは、彼らの制服にも触れておきましょう。映画に出てくる海兵隊は、ちゃんとボタンを留め、比較的きちんとした姿で描かれていますが、これは実際のイメージとも一致します。ただし、実戦において、イギリス海軍では海兵隊員が水兵と同じような作業服(セーラー服)を支給されることもあり、特に非戦闘時にはその方が実用的でした。戦闘時にはもちろん、きちんとした制服姿になります。
ついでに言うと、海軍士官も戦闘時にはできる限り身なりを整えていました。少なくとも清潔な白シャツを着て、ボタンをきちんと留めていたはずです。ところが映画では、艦長が普段からかなりラフな服装で、戦闘に入ってもあまり変わりません。その一方で、士官候補生のミッドシップマンたちは、きちんとした身なりで描かれています。若い彼らが戦闘に備えて身なりを整えるのは自然ですが、艦長だけが「街のチンピラ」のような格好で戦っているのは、やや演出過多でしょう。

映画『Master and Commander』:艦長
また、映画『Master and Commander』には明らかな誤りもあります。翻訳の問題かもしれませんが、フランス側が「ストップ!」と叫ぶ場面です。帆走軍艦は「止まる」ことができません。正しい号令は「惰走に移れ」「セイルを降ろせ」といったものになるはずです。
とはいえ、最後にもう一度本作を褒めておきたいと思います。特に戦闘準備のシーンは非常に優れています。水兵たちが砲弾の錆を落とし、「ピストルと砲の火打ち石を新品に交換せよ」という号令がかかるあたりは、本当に見事です。まさに当時の光景そのものでした。
18〜19世紀の砲弾は、見た目はかなりみすぼらしいものでした。船倉に保管されている間に、水に浸かることも多く、表面は錆だらけでした。そのため、装填・射撃の規定には、「発射の前に砲弾を砲口の縁に軽く打ちつける」という手順が含まれていました。おそらく、錆や埃、汚れをある程度落としてから砲身内に押し込むことが目的だったのでしょう。
当然ながら、戦闘前に砲弾を選り分け、錆を落とすか、油を塗り直すのは望ましい作業でした。

映画『Master and Commander』:砲弾の錆を落とす水兵たち
また、火打ち石の扱いも非常に慎重を要しました。火打ち石は適当に選ぶものではなく、まず石を割って「歯」の形状を整え、最適な形に加工しなければなりません。
兵士一人ひとりは弾薬袋の中に2〜3個の予備の火打ち石を持っている義務がありました。火打ち石の品質にもグレードがありました。火打ち石は縁をギザギザに切った鉛板で包み、これがクランプの役割を果たします。そこから厚手のオイルを含ませた革でさらに巻き、銃のハンマーに取り付けるネジにしっかり固定しました。
このネジを回すための専用ドライバーもあり、ネジ山をつぶさないように慎重に締め込む必要がありました。ネジは鋼鉄製のこともあれば真鍮製のこともありました。
さらに、十分に強く締め込んでおかないと、発射のたびに衝撃で緩んだり外れたりする危険があります。戦闘中に火打ち石が割れたり落ちたりしても予備で交換できますが、その作業には数分を要し、その間火器は使えません。
同時に、火皿に当たる鋼鉄部分が摩耗していないか、刻み目が十分に残っているか、スプリングが正常に働くかなど、常に点検が必要でした。つまり、兵士はつねに自分の火打ち石式銃の状態を気にし、戦闘前には必ず火打ち石の当たり具合を確認していたのです。
総合的に見て、『Master and Commander』は18〜19世紀初頭の多くの現実をよく伝えている優れた映画だと私は考えます。もちろん、ここまで述べたように、いくつかの欠点や歴史的な違和感も存在しますが、それらはいつでも指摘できる類のものであり、「だから映画が悪い」というものではありません。ご清聴ありがとうございました。
この記事が少しでもお役に立てば幸いです。
「Corsairs Legacy - Historical Pirate RPG Simulator」プロジェクトの詳細については、ゲームのSteamページをご覧いただき、ぜひウィッシュリストに追加してください。